活動実績
【交流会を開催しました】2025年度活動 重い病気を抱えるこどもの学び支援活動助成
「重い病気を抱えるこどもの学び支援活動助成」
今年度の交流会を開催しました。
ベネッセこども基金の助成事業では、非資金的支援として、助成団体間の交流や相互の知見・ノウハウ共有等のサポートにも取り組んでいます。その活動の一つとして、全助成団体参加型の交流会を毎年実施しています。
今年の交流会でも、現地交流の熱気そのままに、各団体の活動状況や知見、課題感のシェアや意見交換が実現しました。
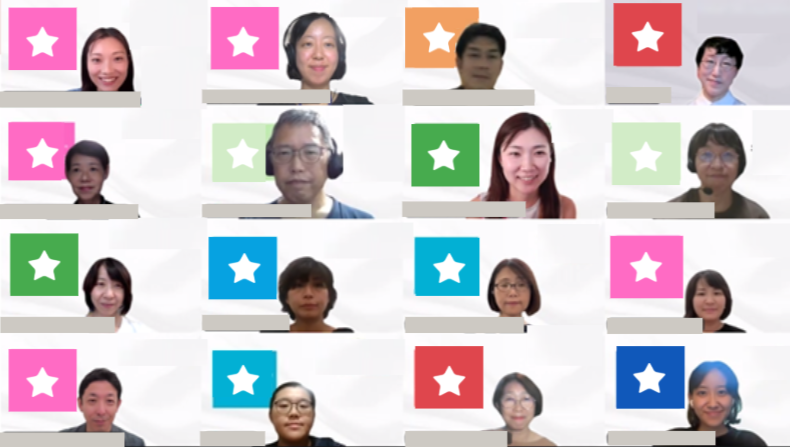
交流会概要
- 開催日時
- 2025年9月5日(金)
- 参加人数
-
・助成事業活動団体 6団体、選考委員、事務局スタッフなど20名
- プログラム概要
-
○参加者自己紹介および各団体の事業内容発表、質疑応答
○小児科専門医・子どものこころ専門医 山口有紗さんによる講演会
○ワークショップ・ディスカッション
○懇親会
〔参加団体一覧〕
・特定非営利活動法人エゴノキクラブ
・認定特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズ
・一般社団法人 Child Play Lab.
・特定非営利活動法人北海道こどもホスピスプロジェクト
・特定非営利活動法人ポプルワークス
・特定非営利活動法人にこり
【交流会第1部】 各団体の活動を知り、課題を共有
まず第一部では、各団体から、活動紹介と助成事業の進捗について発表していただきました。
各団体5分という短い発表時間の中で、活動に参加するこどもたちや大人の様子を写真や動画で臨場感たっぷりに伝えたり、リアルな声を盛り込んだりしてくださり、活動のイメージやこどもたちのいきいきとした様子が思い浮かびました。
今回はオンライン開催のためライブアンケート機能を導入し、発表中にリアルタイムで質問や感想を受け付けました。「応援してくれる病院や団体とどのように繋がりを作っていますか?」「担い手や仲間を増やすために何をしていますか?」といった質問に対しては「実は今まさにその点が難しいと感じていて...!」といった共感のやりとりも多く、普段異なるテーマで活動していても、課題感を共有し他団体の活動から解決の糸口を見つけていただく機会になったのではと感じました。
【交流会第2部】 講演会「こどものウェルビーイング」を高めるために
昼休憩をはさんで、第2部では小児科専門医・子どものこころの専門医である山口有紗さんをお迎えして、講演会「子ども時代とともにある私たちにできること」を実施しました。
日頃から「ウェルビーイング」について考え、取り組みに活かしている団体の皆様ですが、講演会では改めて「そもそもこどものウェルビーイングとはどのように理解すれば良いのか」という前提を丁寧に解説していただきました。
特に、こども時代の愛着形成(アタッチメント)は生涯にわたってその子の心身の健康に影響を及ぼすこと、またこのアタッチメント形成に、家族でない第三者が関われることや、意識すべき大切なポイントを教えていただきました。
また「医療と子どもの権利」については、医療の中で山口さんがこども達に教えてもらったことを交えたエピソードや、こどもの声を交えてお話しいただきました。
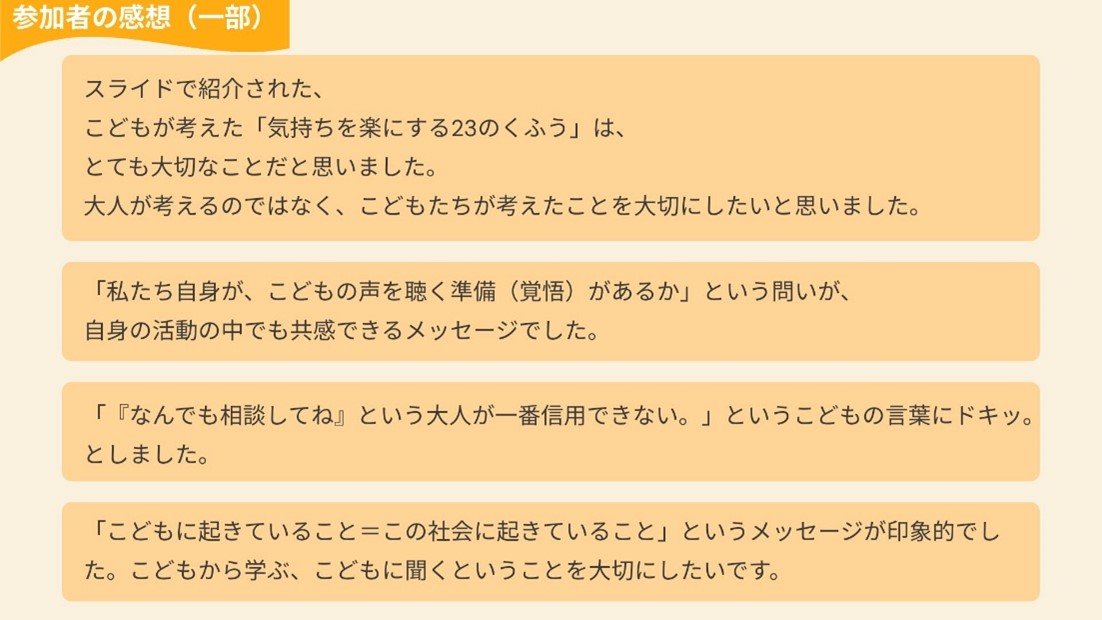
私たちは、「大切な、尊厳ある一人の人」としてこどもに接することができているかを、改めて振り返ることができました。
最後に「ケアする人のケア」として、日頃こどもたちのために活動する団体の皆さん自身・組織自体が、「しんどい」サインに気づけているか、気づいたときにはそれを認め、自らを癒すことの大切さを伝えていただきました。
【交流会第3部】 ワークショップ&ディスカッション
山口さんの講演を受けて、気づきや今後のアクションプランをまとめるワークショップを行いました。
それぞれの団体の活動に重ねながら、今回の講演で「ハッ」とさせられたことや、こどものウェルビーイングを高める上で改めて大切にしていきたいこと、今後新たに取り組みたいことを言語化し、グループディスカッションで団体の垣根を越えて意見交換ができました。
団体の活動意義を改めて感じていただけたと同時に、一緒に取り組むスタッフへの知識の共有や、「こどもを尊重する」「こどもの声を聴く」スタンスを浸透させることで、より一人ひとりのこどもが安心して頼れる存在や居場所になれるよう取り組みたいと意識の変化をシェアしてくださる団体もありました。
【交流会第4部】 オンライン懇親会
最後に、1時間の懇親会を実施しました。オンラインでの実施のため、複数の参加者ではどうしてもやりとりがスムーズにいかない場面もありましたが、日本各地から一堂に会することができるというオンラインの良さもあり、団体間の新たな繋がりを作ってもらうことができました。
交流会に参加した方からは、様々な感想をお寄せいただきました。
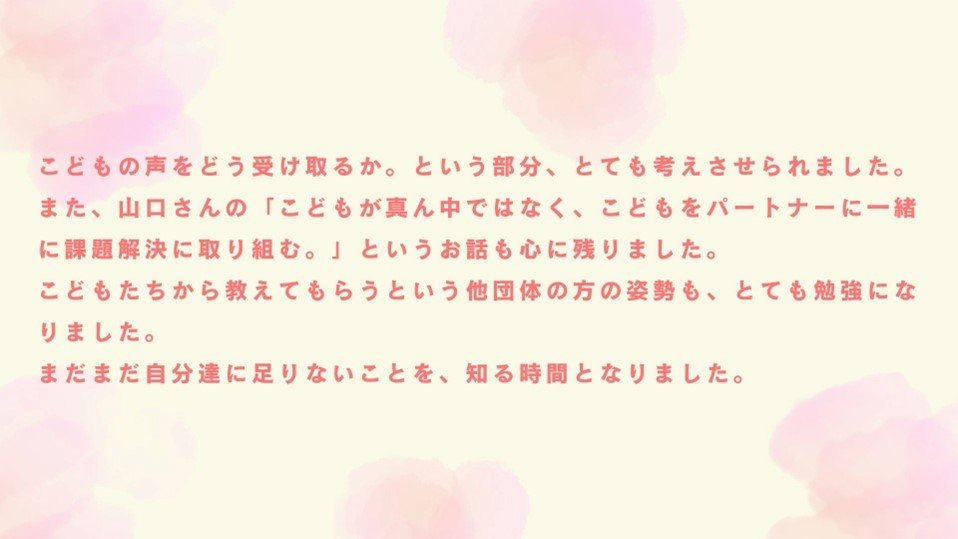
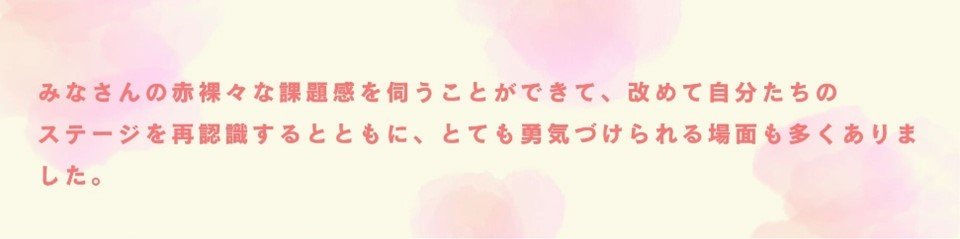
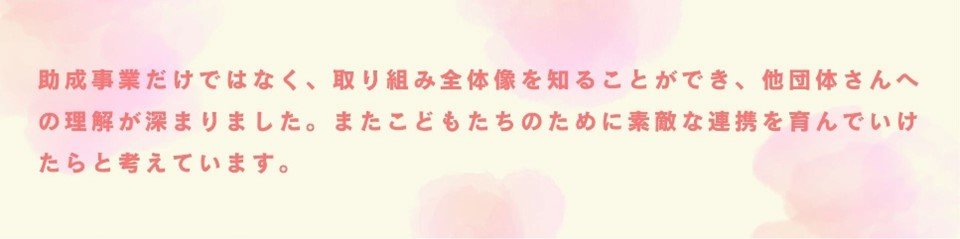
事務局より、交流会を振り返って
今年度も日本各地の団体様と交流することができ、事務局一同もそれぞれの活動への理解が深まりました。また「こどものウェルビーイング」について改めて考えていただく中で、今後のアクションとしては特に、「こどもの声を聴く」というワードが多くの団体から挙げられました。
こどもの声から社会のひずみをとらえ、当事者が本当に必要としている支援を届ける活動が、課題の本質的な解決につながることを改めて感じました。ベネッセこども基金が中間支援組織として果たすべき役割についても、考えを深める機会となりました。
お忙しい中ご参加くださり、有意義な交流会を作り上げてくださった団体の皆様、講演いただいた山口有紗さんに感謝申し上げます。ありがとうございました。
構成/中屋葉月
