コラム
ネット 勉強、悩み相談から遊び相手まで... こどもが生成系AIと『賢くつきあう』ため保護者ができること
専門家コラム:ネット編VOL.54 担当:高橋 大洋
「ママ、この問題わかんない」
「じゃあAIに聞いてみたら?」
そんな会話が、家庭でも当たり前にかわされる時代になりました。
けれど、こどもが勉強だけでなく、友達との悩みや自分の進路まで生成系AIに相談している姿を見たら、「ホントに大丈夫かな」と不安になる保護者も少なくないでしょう。
13歳未満は一人で使用しないことが前提。生成系AI利用の実態と注意点は
生成系AIはいまや、宿題など勉強を手伝うだけでなく、悩み相談や日常会話の相手にもなっています。
「親には言えないこともAIになら話せる」「友達よりも的確に答えてくれる」。アメリカでは10代の若者の70%以上が「AIコンパニオン(※1)」を利用し、33%が「社会的な交流」や「人間関係」構築のためにAIを使っているという調査結果(※2)があります。日本の調査(※3)でも、対話型AIを使う人の約65%が「気軽に感情を共有できる相手」としてAIを挙げており、これは「親友」「母」に並ぶ高さです。若い世代ほど利用頻度が高く、AIに対する信頼も厚い傾向にあると指摘されています。
生成系AIは確かに便利な道具ですが、「AIにすぐに頼ってばかりいると、考える力や知識を深く理解する力が弱まってしまう可能性がある」と指摘されています(※4)。人間には、時間をかけて自分の頭で考える、身体を使って実際に試してみるということが必要なのです。文部科学省からは小中学校でのAI利用のあり方についてのガイドラインも発出されており(※5)、学習への活用には工夫が必要です。また、人間関係を作る力をこども時代にきちんとつけておくことへの影響も心配です。
まず知っておきたいのは、ChatGPTをはじめ、一般向けに提供されている生成系AIサービスは、13歳未満のこどもが一人で使うことを認めていない(※6)という点です。
AIとのチャットは自然な会話のように見えても、実体はインターネット上にあるコンピュータへのデータ送信行為です。送信したデータがその後、誰の目に触れるのか、どう再利用されるのか定かではありません。プライベートな写真、心身の健康に関わる具体的なことがら、各種の個人情報などを書き込むことは避けるべきだと考えられています。
また事実でないことを答える「ハルシネーション」や、回答内容の偏りが生じることも少なくありません。正誤や適切さの判断を含め、回答の取り扱いの責任は利用者側にあります。
AIの回答をどう受け止めるか、判断がしっかりできる年齢になるまではこども一人で使わせることができないのは、そのためです。
では、こどもたちからAIを遠ざけ、スマホやパソコン上で一切使えないように機能制限をするべきなのでしょうか。あるいは、「AIを一切使わない」とこどもに約束させれば済むのでしょうか。
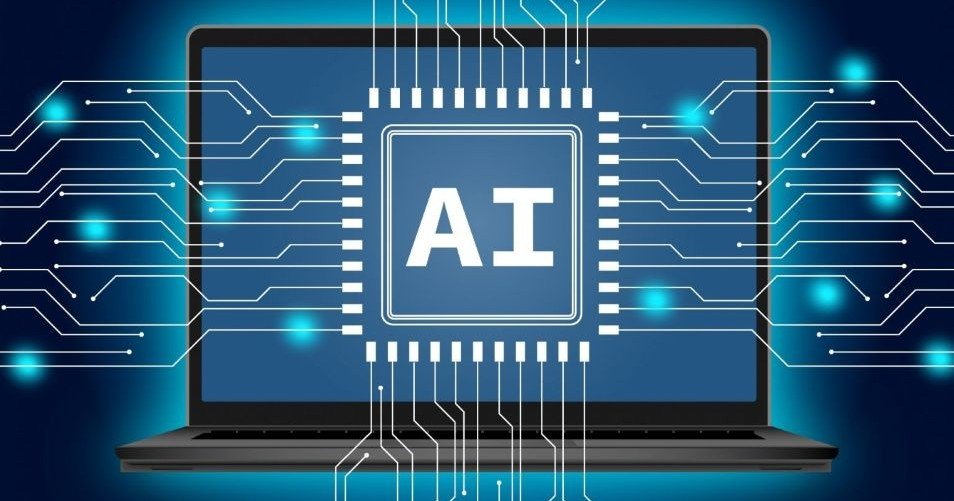
家庭での生成系AIとの付き合い方は?こどもと一緒に、どう使う?
現実には、禁止・機能制限などで保護者が遠ざけようとしても、こどもは勝手にAIを使い始めてしまうものです。
一見、生成系AIサービスのようには見えなくても、検索サービスの一部、他の用途のアプリの一部としてAIが組み込まれているケースもすでに登場しています。AI活用の流れは今後加速していくことでしょう。
したがって、AIの利用から逃げ回るのではなく、AIとの「つきあいかたの基本を保護者とこどもが一緒に考える」機会を積極的に作るほうがオススメです。
こどもと一緒に考える際、おさえておきたいのは以下の三つのポイントです。
① 先に自分で考えてからAIに問いかけ、質問は一度で終わらせないことを原則にする
AIとの対話を始める前に「初めは自分で考えてみよう」とこどもに促しましょう。
「◎◎について教えて」ではなく「◎◎について自分はこう考えるけれど、合っている?」あるいは「◎◎についてこの部分がよくわからないので手伝って」のようにAIに投げかけるのです。
また、AIからの最初の回答に対して、さらに問いかけることも大切です。自分のことばで言い換えて「◎◎は結局こうだったということ?」あるいは「いまの説明のこの部分がよくわからなかったのでもう少し詳しく教えて」のように続けることがおすすめです。
生成系AIはどんな質問を投げかけても、ためらうことなく瞬時にもっともらしいことを答えてくれます。その様子を見ていると、つい全知全能の存在のように考えてしまいたくなりますが、「もっともらしい回答」の一部または全部がハルシネーションだということはいまでもめずらしくありません。何よりも、こどもが自分で考える力を損なうことになりかねません。
AIに問いかけたくなるような疑問が、こどもに湧いているというのは、それだけですばらしいことです。そこからもう一歩だけ踏み込んで、「どこがわからないのか」「自分ではどう考えているのか」を言葉にすること、そして対話をしながら自分の理解を確かめていくこと、疑問をさらに深めていくことが大切です。
② 保護者とこどもが一緒に試す
こどもが13歳未満であればもちろんですが、それ以降も、保護者とこどもの間で生成系AIとのつきあい方を意識的に共有することをオススメします。
最初のうちは、一緒に同じ画面を見ながら「◎◎について、自分ではこのあたりまではわかっているけど、ここから先はよくわからないのでちょっとAIに聞いてみようか」とか「この返事でさらに聞きたいことが生まれたから、この部分についてまた聞いてみよう」のように、AIとのやりとりをしながら、大人の頭の中に浮かんだことを、逐一言葉に出してこどもにも共有しながらAIとの対話を続ける進め方がオススメです。
一方、AIは大人にとっては「道具」ですが、こどもにとってはまず「遊具」です。AIに変な質問をしたり、わざと困らせたりする中で、こどもは「AIとのつきあい方」を体感的に学びます。そうやって遊びながら試行錯誤する時間も、健全な学びの一部です。もちろん、人を傷つけるような使い方(文章や画像の生成など)を認めるわけにはいきませんが、こどもがAIで遊んでいる様子をみても、すぐに注意したりやめさせたりするのではなく、保護者も一緒に面白がることで、こどもの学びはより深く、自分自身のものになっていきます。
こどもが一人で使うようになってからも、「◎◎について、こんなふうに聞いてみたらこんな回答になったよ」と保護者から共有したり、逆にこどもから上手な使い方のコツを教わったりすると、お互いに得られるものが増えるでしょう。その際、AIからの回答の内容だけでなく、「問いかけ方」や「さらにどんな質問をしたのか」といった「活用方法」に焦点を合わせることが重要です。
③ "唯一"の選択肢にしない
人間にはできないほどたくさんの知識を学習しているAIは、わたしたちの知的な作業を支える頼れる相棒です。とはいえ、しょせんは過去のデータを組み合わせて「もっともらしく」答えてくれるだけの存在です。
また、現在わたしたちが利用できるAIアプリは、結局のところサービス業としての競争環境下にあります。有料・無料を問わず、利用者に使い続けてもらうことこそが最優先です。そのため、利用者に寄り添った内容や表現で対話を続けるように、よく訓練されています。利用者の行き過ぎをたしなめたり、誤りを正面から指摘したりするような回答は少なく、利用者の気分を良くさせるような内容・表現になりすぎているという批判もあるほどです。
そして、AIは回答や対話の内容には、一切責任を持ってくれません。その結果を引き受け、わたしたちの人生を、ともに歩んでくれる存在ではありません。
したがって、学習の手伝いをさせる時も、悩み相談をする時も、生成系AIはあくまでも「選択肢の一つ」にとどめておく必要があります。保護者・友だちなど、こどもの周囲の人たちとの関係が、AIとの関係と違うのはどんな点なのか、機会を見つけてこどもと話し合っておくことが大切です。
時代の変化を受け止め、前向きにとらえるために
インターネットの普及以降、社会の変化はより速く・大きくなっています。世界は一段と狭くなり、諸外国の社会情勢を見ても、いままでに経験のないことばかりが起きていると感じられるかもしれません。子育て中の保護者にとっても本当に大変な時代です。
ただし、この変化を前向きに受け止めることは十分に可能です。わたしたち人間には本来、現実を柔軟に理解し、受け止めた上で、能動的に働きかけ、よりよい形へと変えていく力が備わっているはずです。生成系AIは人間のアシスタントとして、わたしたちの力をさらに高めてくれるために生まれた技術なのです。
AIは、世の中のあらゆる仕事の進め方に、すでに大きな変化を与えつつあります。さまざまな日常業務の補完だけでなく、さらに価値の高い成果を生むようなAI活用が一人ひとりに期待されています。
一方で、近い将来AIに置き換えられてしまう業務があるとも言われています(※7)。でもその本当の意味は、わたしたちに求められる技能がこれまでとは少し違うものになるということです。たとえば、自分自身が時間をかけて経験してきたこと(身体性)から生まれてくる「問いを立てる」力、共感力・対人スキルといった周囲の人と関わり、協力する力といった、人間にしかできないことばかりです。
いまのこどもたちが社会に出る頃には、AIとの共存・協力関係は、ごく当たり前のものになっていることでしょう。わたしたち保護者には、本稿で挙げたポイントに配慮しながら、こどもと生成系AIとの出会いを有意義で、バランスのとれたものにすることが期待されています。
※1ChatGPTなどの汎用型生成系AIツールではなく、話し相手専用として仕立てられたAI利用アプリのことを指す。
※2 Common Sense Media「Talk, Trust, and Trade-Offs: How and Why Teens Use AI Companions」(2025年7月)
※3 株式会社電通「対話型AIとの関係性に関する意識調査」(2025年7月)
※4 Michael Gerlich「AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Of oading and the Future of Critical Thinking」(2025)
※5 文部科学省「生成AIの利用について」(2024)
※6 学校向けの生成AIで13歳未満の利用が認められているケースがある。
※7 Forbes「本当に「AIの影響が小さい仕事」は何なのか? MSリサーチの調査が示す新データ」(2025)
高橋 大洋さん
フィルタリング開発会社での勤務をきっかけに、「ネットとのつきあいかたをオトナにも分かりやすく」に取り組む。こどもとネットについての調査・研究や教材開発、指導者養成の他、保護者・教員向け研修講師としても活動。著書(共著)『学生のためのSNS活用の技術』(講談社)。こどもたちのインターネット利用について考える研究会 事務局、一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA) 事務局、ポールトゥウィン株式会社 契約パートナー、小樽商科大学・帯広畜産大学・北見工業大学 非常勤講師。札幌市在住、こどもは18歳と15歳。
