助成団体紹介
2024活動報告|外国につながるこどもの学びに活用できる教材が完成し、全国に提供
特定非営利活動法人 eboard
3年目の助成期間を終え、活動の成果をご報告いただきました。事業の詳細などは以下からご覧ください。
2022年事業紹介 外国人散在地域での支援をサポートする「外国につながる子を対象とした日本語ICT教材」の検証・開発事業 2022活動報告|外国人散在地域での支援をサポートする「外国につながる子を対象とした日本語ICT教材」の検証・開発事業 2023活動報告|外国につながるこどもが学べる日本語ICT教材を、試行錯誤しながら開発
事業の目的 事業の内容 事業の結果 事業の成果 課題および今後の展望 3年間の助成を振り返っての感想
事業の目的
日本語指導を必要とする児童生徒数が年々増加する一方で、支援者不足や財源確保の難しさから、日本語指導や学習支援の体制を十分に整えることが全国的に困難な状況となっています。そんな中、日本語による学習に難しさを抱えるこども達への支援課題の解決を目的として、専門性の高い支援者がいない環境であっても学習者が自立的に学習を進められる教科学習用のICT教材を開発し、現場に広めることをゴールに事業を進めました。
特に3年目は、
①2年目から継続して開発に取り組んでいた算数・数学教材の開発を完了し一般公開すること
②支援現場の協力を得て効果的な活用方法をユースケースを開発し、教材とともに公開すること
③教材を支援現場70箇所に訴求すること
をめざし、活動を行いました。
事業の内容
【1年目】調査・分析と教材の骨子固め
教育現場のニーズ調査(アンケート、ヒアリング等)を通じて、特に教科教材の不足と支援現場の課題を把握しました。専門家や協力団体との議論を重ね、小学5年~中学3年の算数・数学を対象に、視覚情報を中心とした学習補助教材を開発する方針を固め、基本仕様とカリキュラムの骨子を策定しました。
【2年目】制作体制の構築と試練、一部先行検証
1年目の教材仕様とカリキュラムを元に教材制作に着手しましたが、制作ノウハウの共有や体制構築の遅れから計画を一部修正しました。プロジェクト体制を再構築し、人員を増強して制作を本格化させるとともに、完成した一部教材については協力校2校で先行的に活用し、その有効性を確認しました。
【3年目】教材完成・公開と全国への普及
教材作成を完了し、ウェブページを作成して「やさしい算数・数学」としてPDF形式でダウンロード可能な形で一般公開しました。並行して、公立学校や民間団体と連携してユースケース開発を進め、教材の具体的な活用方法を模索しました。最終的に、2箇所の民間団体での活用をユースケースとしてウェブページに公開しました。また、広報活動にも注力し、全国34都道府県の学校や団体152現場を通して約2000人の子どもたちに教材を届けることができました。
事業の結果
- 「外国につながる児童生徒の日本語指導における教材活用アンケート」結果報告書
- 「やさしい算数・数学」紹介サイト
- 「やさしい算数・数学」教材(上記サイトからダウンロード可能)
- 「やさしい算数・数学」活用のユースケース(上記サイトから閲覧可能)
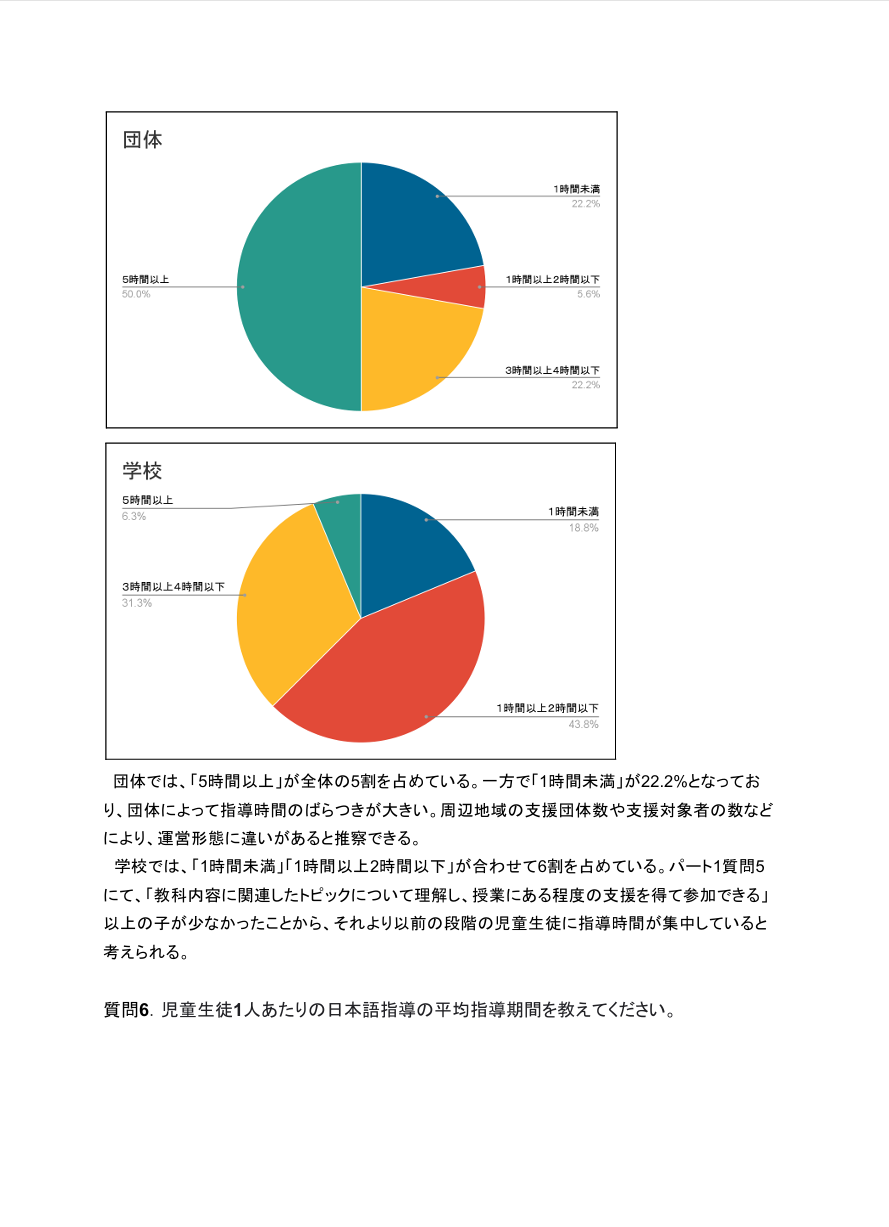
事業の成果
成果①:外国につながるこどもたちの学習機会の拡大・困難の解消
開発された教材「やさしい算数・数学」が、全国34都道府県の162の学校・団体に届けられ、約2000人超のこどもたちへの利用が見込まれるようになりました。学習内容を視覚的に学べることで、日本語能力が十分でないこどもでも算数・数学の教科学習に取り組みやすくなり、「本教材の活用で学習が楽しかったというこどもの言葉が聞かれた」など学習への肯定感につながりました。また、これまで適切な教材が不足していた層(特に日本語初期指導終了後、通常学級で困難を抱えるこども)に対して、学習支援の選択肢を提供できました。
成果②:支援範囲の拡大・支援の捉え方の変化
これまで、必ずしも日本語指導や教科指導の専門家ではないボランティアスタッフが支援の中心となっている現場が多くあった。そうした場では学習支援に対応できる教科が限定的であったり、教科担当者がいる時間に少人数のみ支援可能であったりと、支援の提供範囲が限定的であった。本教材は学習者自身が自立的に取り組むことができるため、支援者のスキルによらず学習支援を進めやすくなった。また、そうした支援を通して「教える支援」から、「こども達が学習を進められる環境を整える支援」へと支援の捉え方に変化があったことがヒアリングを通して伺えた。
課題および今後の展望
本事業を通しての主な課題は、①助成期間中、公立学校において本教材の継続的、効果的な活用方法の蓄積が十分に進まなかった点、②算数・数学以外の教科における支援が必要であること、があげられます。
課題①を踏まえ、弊団体では2025年度に教育委員会と連携して本教材の公立学校での活用促進活動を開始しています。今後も公立学校への普及活動を継続的に行い、ユースケース開発につなげたいと考えています。また、課題②に対しては、生成AIを活用して日本語を平易で理解しやすい「やさしい日本語」に変換することでの支援のあり方を模索しています。支援現場と連携して効果的な支援方法を確立することで、外国につながるこどもが抱える多様な課題の解決に貢献できると考えています。
加えて、本教材公開後、特別支援教育の現場からも教材のダウンロードがあり、そうした領域でも日本語理解を前提とする学習に伴う困難があること、視覚情報を用いた教材が有効であることが示唆されました。今後、特別支援を代表とする他領域に本教材を展開し、その活用効果を検証していきたいと考えています。
3年間の助成を振り返っての感想
本事業を通して、私たちNPO法人 eboard にとっては経験のなかった「日本語指導を必要とするこどもたちへの学習支援」という新たな領域に挑戦することができました。
当初は手探りの状態でしたが、ご協力いただいた専門家の方々、日々子どもたちに向き合っている教育現場の支援者の方々から貴重な知見とご助言をいただき、視覚的な支援を重視した算数・数学教材「やさしい算数・数学」を開発することができました。その結果、当初の想定を大きく超える数の学校や団体、そして何よりも多くのこどもたちに教材を届けることができたことを大変嬉しく感じます。同時に、支援者の方々からの応援を受け、NPO法人eboard の活動への期待も感じました。今後も、様々な困難を抱えるこども達がその困難を解消できる環境を整え、それを広げていけるよう、支援者の方々と協力しながら活動を進めてまいりたいと思います。
3年間の事業の途中で計画の変更もありましたが、最後までご支えてくださったベネッセこども基金の皆様に心より感謝申し上げます。
中村 孝一 さん
大学在学時、学習塾や学習支援現場での経験から、こども達の学習課題を痛感。外資系コンサルティング会社勤務を経て、eboardを創業。2016年より、世界経済フォーラムGlobal Shapers Osakaハブメンバー。
