助成団体紹介
2024活動報告|貧困に悩む家庭のニーズに合わせて学習や生活の支援を実施
一般社団法人 みらいTALK
3年目の助成期間を終え、活動の成果をご報告いただきました。事業の詳細などは以下からご覧ください。
2022年事業紹介 こどもの生活・学習支援事業 Juice Class+プラス 2022活動報告|少額寄付と高校入学準備金クラウドファンディングの実施 2023活動報告|生活・学習支援の場が充実。家庭との信頼関係や保護者の意識にも変化が
事業の目的 事業の内容 と活動の経過 事業の結果 事業の成果 課題および今後の展望 3年間の助成を振り返っての感想
事業の目的
私たちは不登校・虐待・いじめなどこどもたちが直面している問題の背景の一つに貧困の問題があることに気づき、学習支援を切り口にこどもや保護者を支えることができるのではという思いで支援を行ってきました。実際に始めてみると想定以上に参加希望者が多く、また実際学習支援参加後にこどもや家族が良い状態に変化していく事例を多数経験し、もっと多くのこどもが参加できるようにしたい、そして内容もブラッシュアップしたいと考えていました。
また、無事高校に進学しても、部活に必要なお金が払えない、定期代が払えないなど多くの困難がこどもたちを待ち受けていることも知りました。支援の少ないとされる高校生世代の課題について実態を知ることが必要だと考えました。
そして、週1回の学習支援には来るけれど、学校には全く行けないこどもたちや、不登校のまま中学卒業後も在宅でゲーム漬け昼夜逆転になっているこどもたちなどと出会い、私たちに何かできることはないかを探っています。こういったことも助成3年間を通じて出会った課題として検討したいと考えています。

事業の内容と活動の経過
・生活・学習支援の会場を2会場から1会場増設。あわせて学習を担当する学生ボランティアも増員し、1:1に近い学習支援体制を組むことができました。また、中3生のための夏季講習・夏季合宿など学習支援の充実をはかることができました。
・生活支援としては、家電が壊れたままで修理や新規購入ができずにいるご家庭の存在がわかり、他の支援団体からの寄付で家電を無償で提供。あわせて関係機関とともに屋内の清掃も実施。こどもの生活が劇的に変わった事例も経験しました。
・助成1年目にはクラウドファンディングで高校入学のための資金を2,977,250円集めました。その資金で学習支援卒業生の高校入学を支援することができました。通学のための自転車の購入や定期代の補助など、直接的に高校に通うために必要な経費にあててもらうことで、「お金のことを考えると、入学を心から喜べなかった。涙が出るほど嬉しかった」などの言葉を保護者からいただきました。その後は、中学卒業時に、入学後必要になるリュックやスニーカーなど、本人の希望する物を選んでプレゼントする形で支援を続けることができました。
・義務教育年代まではあった支援が高校生年代になると途切れてしまうことが多く、こども自身が困っても頼るところが少なくなるという現状があります。そこで必要な家庭には、高校生年代になっても学習支援とともにお弁当の提供など生活支援も継続。また、不登校のまま中学を卒業。在宅となっているお子さんを学習支援で受け入れ、大学生や他児との交流、行事の経験など社会参加の入口となる役割をはたしました。




事業の結果
・生活・学習支援の利用児童も3年間でのべ1,540人から2,155人と増加しました。また、学生ボランティアも2024年度はのべ約2,000人が参加。ほぼ1:1の支援を実現しています。その結果、全員が志望校に進学しました。
・生活に必要な家電(洗濯機や冷蔵庫他)の提供は4家庭に行いました。また、ボイラー等の故障で家庭での入浴が数年にわたってできていないケースもあったため、学習支援の会場で毎週シャワー浴を行ったこどもたちも毎週5人に及びました。
・必要なケースは保護者同意のもと児童相談所や社会福祉課を巻き込み、一緒に支援することで継続的な家庭支援につながっています。
また、保護者の入院のため、数日を当法人のスタッフと学生ボランティアが一緒に過ごすことで通学を保証できた中3生もありました。
・高校入学時の金銭的な支援や物品による支援は、経済的に厳しいご家庭からは非常に喜ばれました。私たちも実際に入学にかかる費用を確認することで、隠れ教育費の問題を切実に感じました。
・助成1年目は、当法人の生活・学習支援を卒業したお子さんをフォローするところから始めた高校生支援でしたが、助成2年目・3年目は、行政などから紹介された中学卒業後どこにも所属できていないお子さんの受け入れも行っています。
・3年目には定時制高校に通うこどもたちにフードパントリーを行い、その世代のこどもたちの実情や悩みについてアンケート調査を行いました。そこには、自身や家族の病気や障がいなどで悩んでいたり、71%のこどもが過去に不登校を経験していたりといった実態が示されていました。
事業の成果
・助成前に比べ、生活・学習支援の実施会場を1か所増やしたことで利用するこどもはのべ人数で1.4倍となり、それに伴い大学生の参加者も増え、最初の目標の1つである量的な充実は十分はかれたと思います。質に関しても、中3生勉強合宿や夏期講座などの実施や、学生への研修の充実をはかることができました。
・高校入学後もここに通い、国立大学に合格してボランティアとして後輩の勉強をみに来てくれている学生もでてきて、この事業の成果を感じています。助成3年目には学生の代表が日本こども家庭福祉学会で、この活動をまとめて発表しています。学生自身もこの3年間の活動の中で、単なる補助ではなく、自分たち自身で考え、積極的に事業提案してくれるまでになったと感慨深く思います。また、大規模な団体と違ってこども一人一人そして家庭が見える形で活動できているからこそ、家族の問題を一緒に考え、それぞれの家庭に必要なオーダーメイドの支援ができたと思います。
・なかなか専門機関につながらなかったケースも、私たちの活動の中から生まれた信頼関係を軸に、徐々に他の機関の支援も受けいれるようになっていきました。そうして家庭環境が整うことでこどもたちも学校を休むことが減ったケースもありました。
・こうした活動を持続可能にするために、当法人のパンフレットの作成、事業報告の充実、ホームページの刷新をはかりました。まだ、直接的な寄付の増加にはつながっていませんが、活動に対する問い合わせや協力の申し出は徐々に増えています。他の団体からの申し出で、昨年度はロープクライミング教室など、普段なかなか体験できないスポーツを経験することができたり、食事の提供の申し出があったり、地域の他団体と協働してこどもたちやその家族の生活を豊かにする活動ができるようになってきました。
・2024年度は浜松市でもこども計画策定の年にあたり、私たちは他のこども支援団体に声をかけ、「浜松こどもまんなかネットワーク」を立ちあげました(立ち上げには10団体が参加)。一般の子育て支援団体とも一緒になって、市のこども計画がより良いものになるよう働きかけることができ、2025年度も活動を続けていく計画になっています。
これらのことは、生活困窮家庭の支援にとどまらず、様々なマイノリティのこどもたちも含めた(より意識した)こども支援を官民一体で展開していく基盤づくりにつながったと考えています。
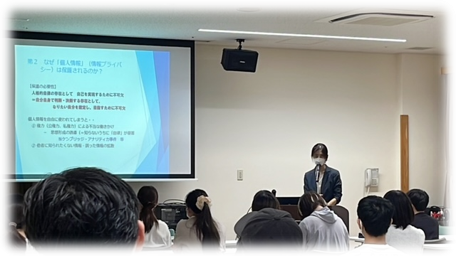


課題および今後の展望
最も大きな課題は、団体の維持だと思います。様々な課題を抱え、苦しんでいるこどもたちに出会うと支援に必要な時間や労力をスタッフ個人に頼って行ってきた部分が大きいのが実際です。
頑張ってきた結果、大きな成果をあげているけれど、事業の継続という観点で見ると同じ温度で維持・発展させることは難しいと思われます。やはり、みらいTALKという団体の仕事として事業を継続できるよう経営の視点を入れていかなければと法人内でも検討を初めています。
今後は、本助成を受けて取り組み始めたこと。現状支援の少ない高校生世代の支援(調査・分析を含む)や不登校児童や家庭環境に課題を抱えるこどもたちの支援。について取り組んでいきたいと考えています。
3年間の助成を振り返っての感想
生活困窮家庭のこども支援として始めた生活・学習支援ですが、現在のこどもを取り巻く問題は様々な要因が重なり合い、かなり深刻な状況だということがわかってきました。
しかし、このタイミングで助成を受けられたことで、支援の量も質も充実させることができました。また、企画していただいた研修や情報交換会から自分たちが困っていることについてとても有益なお話を伺うことができました。助成がなかったら、諦めていた問題も、様々な角度でご支援いただいたお陰で勇気づけられ挑戦できたと思っています。困っているこどもたちの状況を行政に伝え、必要な事業の提案など、それまでしてこなかった動きも法人として行うようにもなり、それが少しずつ実を結ぼうとしています。
また、こども支援先進的な取り組みをしている団体を視察することができ、多くのヒント・学びを受けました。ベネッセこども基金様には深く感謝いたします。
平野 浩一 さん
これまで小児科医としてこどもの発達や心身の問題・症状の臨床に携わってきました。 多職種のスタッフと一緒に仕事をしてきて、こどもや家族を支えるためには、診察室の診療だけでできることの限界や、見えづらいものに気づかされてきました。志のある仲間の協力に支えられて今の活動があります。
浜松市発達医療総合福祉センター
センター長
